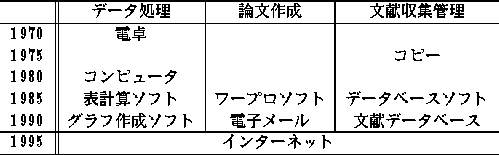
ところで、「研究」とはそもそも、「情報」の流れを操作して 価値を生み出す営為であるから、コンピュータの有無やその進 化の程度に関わらず「研究における情報処理」自体は確固とし て存在してきたわけである。そして、コンピュータの存在と進 化は、その補助的手段(と信じたい)として「研究」の促進に 寄与してきたというわけである。では、いったいそれはどのよ うに貢献してきたのか。ここでは、「研究」の内容として、1) データ処理、2)論文作成、3)文献収集、の3つをあげ、そこで のコンピュータなどの機械の進化が果たしてきた貢献の履歴を 私の利用状況を前提として整理してみた(表 2.2)。 もちろん、研究の核ともいえる「実験・調査」においてコンピュー タが果たしてきた役割はきわめて大きいわけであるが、個別の 機械の開発などの影響を総覧することが困難なのでここでは省 略した。
: コンピュータ環境の変化と「研究」への貢献
まず第一に述べなければならないことは、「コンピュータ」と いう商品が一般に供されるようになったのは1960年代のことと はいえ、それは当初きわめて特殊な分野の特別な装置とみなさ れており、我々一般の研究者が手にできるものではなかったと いうことである。その後、1970年代に一部で「マイコン」とし て趣味的な広がりをみせたとはいえ、それが「普通の研究者」 の間に広く普及したのは1980年代のことであった。それ以前の 研究は、かろうじてその10年ほど前に普及した「電卓」によっ て数値が処理されるのが精いっぱいで、成果は全て原稿用紙に 手書きでまとめられていたのである。そしてそのころの私たち にとっての「コンピュータ」とは、「それまで自在に使いこな してきた電卓のお化けとしての畏敬の念を与えるもの」であり 「プログラミングという特殊技術を要する難解な装置」と認識 されていたはずである。
ところが、コンピュータが急速に普及した1980年代には、「機 械」であると同時に「ソフト」という目に見えない装置によっ て個別のニーズに応えるものとして喧伝されていったため、そ の緊張関係に緩みが生じた。具体的に言うと、「表計算ソフト」 はメモリ付き電卓の便利な姿であり、「ワープロ」は「タイプ」 にかわる清書装置、「データベースソフト」は文献カードでの 管理を一手に引き受けてくれる整理文具として、いわゆる「機 械音痴」と自称する人々に据えられた壁を徐々に瓦解していっ たのである。いわゆる、MS-DOS時代である。もちろん、当時か ら自分が頭の中で確かに把握できる電卓に比べて「目に見える 部分」が少ないコンピュータに警戒心を示す研究者もいたが、 そのような警戒心はその後の普及の中で静かに消えてしまった ように思われる。1980年にはトレーシングペーパーとステンシ ルによって記されていた図表は、1990年にはほとんど全てグラ フィックソフトによって作成されるようになっていった。
ところが、そのように悠々自適とパソコンが利用されている間 に、その背後ではネットワーク化が進められていたのである。 そして、1980年代後半になるといわゆる「パソコン通信」によっ て電子メールの利用者が増えるとともに、1990年には多くの研 究者が文献データベースを利用するようになっていた。前者は 1970年代の「マイコン」と類似した趣味的な意味あいが強調さ れたため、本格的に我々が熱中するようになるのには若干の時 間を要したが、後者については学者の牙城とも言うべき図書館 の延長であったために、研究者がその虜になるのにはさほどの 時間がかからなかった。
そして「インターネット」時代を迎える。もともと、「インター ネット」とは、組織毎に整備された個別のネットワーク(LAN) を相互に結びつける大規模ネットワークという意味あいの名称 であるが、もはやそれは、ハード面では電話回線や衛星通信と の区別をつけられない社会基盤として広く認識されているし、 ソフト面では放送、通信、出版など社会におけるほとんど全て の情報媒体を総括するものとして、その行方が注目されている。 例えば、現時点で既にコンピュータはファックスの機能を包含 する(すこし不便なファックスといえる)し、コンピュータに 付属したマイクとスピーカーを使用してインターネットから一 般電話に(市内利用料金だけで)かけることも可能になってい る(当然、コンピュータ間の「電話」も可能で、その場合はタ ダ)。私たち研究者の業績評価の指標として保持されている論 文出版という文化形態にも、徐々に電子化の影響が及んでいる。 そして、私たちはすでにその新しい文化の虜になり始めている。
ちょっと視点を戻してみよう。1980年代後半に一世を風靡した MS-DOSの3種の神器(ワープロ、表計算、データベース)は、 1990年代にはお互いの垣根が少なくなってきて、通信機能も含 めた統合ソフトとして広まっている。この変化を私たちは自然 に受けとめている。では、現時点で機能的に区別されている電 子メールと論文出版の融合を私たちは平静に受けとめられるで あろうか。電子メールによる研究交流は容易にメイリングリス トやニュース(電子掲示板)を通じて不特定多数の人々への情 報公開へと発展可能だし、ホームページでの情報交換と同じく ホームページでの論文刊行との間には、少なくとも著作権上の 区別はない。違いは、それを提供する組織のクレジットの程度 である。ところが、そのクレジットは、生身の人間が交流する 学会大会や図書館に陳列される物理的な学術雑誌によって保証 されている。結局のところ、電子的ではない人間の「ネットワー ク」がその根拠となっているのである。ところが、冒頭に述べ たように、(少なくとも私は)電子ネットワークの虜になって いる。その「インターネット時代」に私たちが如何なる「研究」 をするか、そして、「体育学」が如何に発展していくかが、 2000年代には問われることになるのであろう。