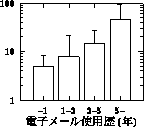
図 3.2: 電子メールの使用歴(横軸:年)と一日あたりの送受信件数(縦軸:件/日)。
図1にメールの使用歴と一日あたりの送受信数との関連を示し た。使用歴が長くなるほど処理件数が多くなっていることがわ かる。一般に、長く使っているほど自分のアドレスが知られる ようになり送受件数が多くなっていくという解釈は自然だが、 今回の対象者については、他群と有意差があったのは「5年超」 群だけであり、5年以下の群間には有意差が認められなかった。 5年前の92年5月といえば、まだ日本ではWindows3.1さえ普及 していない頃で、この頃から既に電子メールを使っていた人々 は、研究者の中でも特にコンピュータに馴染んでいたものであ ると考えることもでき、この差のうちどの程度が使用年数に起 因し、どの程度が個人の適性・特徴に起因するのかについては、 不明である。
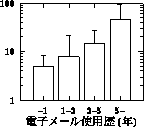
図 3.2: 電子メールの使用歴(横軸:年)と一日あたりの送受信件数(縦軸:件/日)。
図2に、メールの使用歴と一件あたりの処理時間(所要時間を 送受信件数で除した値)の関係を示した。3年以下では一件あ たり4分強であるが、3年以上になると処理時間が短縮し、使用 歴5年以上の群では1.4分/件であった(他群と有意差あり)。 処理時間は送受信件数とも相関があり、件数が多くなるにつれ て一件あたりに費やす時間が短くなっていく傾向がうかがえる。 1日あたりの送受信件数が2件以下の群(11名)の平均処理時間 が5.2分/件であるのに対して、1日あたり8件超の群(20名)で は平均が1.7分/件、最大でも5分/件しかなかった。
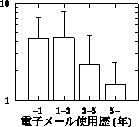
図 3.3: 電子メールの使用歴(横軸:年)と1件あたりの処理時間(縦軸:分/件)。
図3に、一日あたりの送受信件数とスプールチェック回数との
関係を示した。一日あたりの送受信件数が多くなるほどスプー
ルのチェック回数が多くなる。この中には「自動受信」に設定
して、メールの到着と同時に読み込むものや、一定時間毎にチェッ
クするものもあり、最高は250回/日であった。これらの「自
動受信」に設定されたデータを除いて、実際に「メールをチェッ
クしようとする行為の頻度」を集計すると、一日あたりの送受
信件数が2件以下の群では (n=11)、2〜8件で
は
(n=11)、2〜8件で
は (n=26)、8件超の群では
(n=26)、8件超の群では (n=16)
となった。
(n=16)
となった。
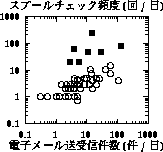
図 3.4: 一日あたりの送受信件数(横軸:件/日)とスプールチェック頻度(縦軸:回/日)。 は自動受信を表す。
は自動受信を表す。
図4に、一日あたりの送受信件数と所要時間との関係を示した。
一日あたりの送受信件数が多くなるほどメールの処理に要する
時間が長くなっている。これらをグループ別に集計すると、一
日あたりの送受信件数が2件以下の群では 分、2〜
8件では
分、2〜
8件では 分、8件超の群では
分、8件超の群では 分となっ
ていた。
分となっ
ていた。
以上の集計結果から、今回の調査で対象とした人々のメールの 使用歴と利用状況の相関をまとめると、図5ようになる。すな わち、メールの使用歴が長いほど一日あたりの送受信件数が多 くなる。ただし、それが時間経過に伴う必然かあるいはコーホー トの影響かは不明だが、少なくとも送受信件数の増加はチェッ ク頻度の増大をもたらす。そしてそれは、一件あたりの所要時 間を短くするものの、一日の中でのメールに携わる時間の総量 を長くする。ただし、メール使用歴と一日の所要時間との相関 関係は弱く(p=0.06)、必ずしも長く使っているほど時間が多 くなるわけではない。メールの送受信件数が多くなるかどうか、 すなわち、日々の他者との情報交換をメールに依存するかどう かが、その所要時間を決定する鍵になるものと考えられる。
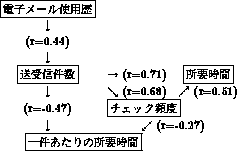
図 3.5: 電子メール使用歴と利用状況の相関。(rはスピアマンの順位相関係数)
今回の調査では、電子メールの必要性などについての意識も質 問した。しかし、もとから、「電子メール」で回答を寄せてい るわけであるから、その意識に特段の差異は認められず、他の 質問項目との関連も見いだすことができなかった。